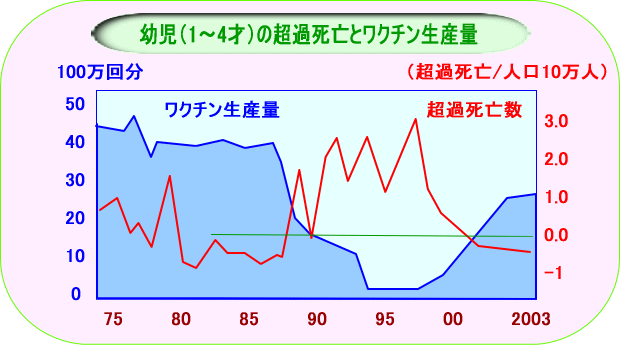
インフルエンザの最も確実な予防法は流行前にワクチンを接種することです。
特に、抵抗力の弱い小児や高令者、気管支喘息、糖尿病、高血圧などの慢性の病気を持っている方などは、インフルエンザにかかると重症化することがありますので、積極的に接種しましょう。
インフルエンザは、基礎疾患を持っている人や、免疫力が低下している高令者では、大きな脅威ですが、最も罹りやすいのは、インフルエンザの感染経験の少ない小児です。かって(1960年頃)、学童が集団生活する学校から、インフルエンザは流行始め、社会へと拡がってゆくという考え方がありました。また、その当時はインフルエンザは「冬に流行するカゼ」程度にしか考えられていませんでした。
つまり、感染拡大の源である学校を押さえれば、「流行拡大を阻止」できるのではないかという 「学童防波堤論」と言う考え方がありました。このような考え方に基づいて、1962年に、インフルエンザの流行を阻止するため、全ての学童にインフルエンザワクチンの集団接種が行われるようになりました。
その後、ワクチン品質は向上し、1972年にエーテル処理によるウイルス脂質成分の除去法が導入されて、現在のワクチンが実用化されました。現行ワクチンは副作用も少なく、世界的に見ても安全性の優れたワクチンと高い評価を受けております。
しかしながら、学童の集団接種方式に関しては、様々な議論がありました。例えば、「学童全員にワクチン接種を強制するのは人権問題ではないか?」とか、「学童だけに接種しても流行状況は変わらないのではないか?」など、学童の集団接種に対する様々な批判が起こってきました。この様な情勢の中、次第にワクチン無効論が唱えられるようになり、特に1987年に発表された「前橋レポート」は『インフルエンザワクチンには流行を阻止する効果はない。』という極めてインパクトの強いものでした。
さらに、重篤な副作用を疑われる症例について、はっきりと因果関係を調査することができず、行政の対応が必ずしも適切ではなかったことが強調され、また、いろいろな誤解から生じたインフルエンザワクチンに対する不信感がマスコミによって過剰に報道されるようになりました。その結果、1980年代後半からワクチン接種率は急激に低下していきました。
当時、ワクチンが効果がないと言われた理由として、現在の医療水準から見ると次のようなことが考えられます。
1.インフルエンザと普通のカゼの区別がつかなかった。
インフルエンザワクチンを接種しても普通のカゼにはかかります。昔はインフルエンザの検査がすぐできませんでしたので(現在の迅速キットが使われるようになったのは、1999年からです。)、そのため普通のカゼにかかっても、インフルエンザと誤って診断されていた場合が多く見られました。
2.インフルエンザの初期症状が見られただけで(熱がでただけで)、ワクチン無効としていた。
もともと、インフルエンザワクチンは体内に入ってきたインフルエンザウイルスの増殖を防いで、重症化を予防するワクチンであり、直接の感染を防ぐことはできません(次項:「インフルエンザワクチンの有効性」を参照)。
医師間でもそのようなことがよく理解されていなかったため、ワクチン接種しても、少しでも熱が出たりすると無効とされていた場合が多々あります。
つまり、当時の医療レベルでは、普通のカゼもインフルエンザも区別がつかず、ちょっと具合が悪ければインフルエンザと診断されていました。また、インフルエンザワクチンの本来の働きである「重症化を予防する」ということも全く評価されず、誤った判断の基にインフルエンザワクチンは効果がない。とされていたように思われます。
一方、これらの批判とは別に、80年代後半には、インフルエンザのような感染症は「個人の責任で防止すべき」であるという個人防衛の考え方が見られるようになってきました。1994年の予防接種法の改正に際しては、基本的にこの考え方が導入され、インフルエンザワクチンは定期接種からはずされて任意接種になりました。つまり、接種するか否かは、個人の自由(個人が決めること)となりました。
しかし、この結論に至った経過や説明が不十分であったため、多くの人たちには、「国がインフルエンザワクチンは効果がないから、学童の集団接種を廃止した。」との誤解が生じました。そのためワクチン接種を受ける人は極端に減ってしまいました。
これまでわが国では、インフルエンザワクチンの効果については、「流行拡大を阻止」という観点からしか議論されてきませんでした。つまり、「インフルエンザワクチン本来の働きである重症化を防ぐ」ということについての議論が殆どなされていませんでした。その結果、インフルエンザは「冬に流行するカゼ」、インフルエンザワクチンは「流行拡大を阻止」できないワクチンという『間違った考え方』が広まってしまいました。
ところが、ワクチン接種を受ける人が少なくなった1990年代後半から、高令者や、施設入所者のインフルエンザによる入院、重症例が報道されるようになり、「インフルエンザが命にかかわる病気である。」という意識が次第に広がってきました。
日本では、インフルエンザに罹患すると重症化すると思われる人たち、つまり、ハイリスク群(注1)に対するインフルエンザワクチン接種を積極的には行ってこなかったので、ハイリスク群におけるワクチンの効果についての詳しい研究成績はほとんどありませんでした。
(注1)ハイリスク群
①.65歳以上の高令者
②.施設入所者
③.基礎疾患を持つ小児及び成人(気管支喘息・肺気腫・心疾患・糖尿病・腎不全等)
④.妊娠28週以降の妊婦
⑤.乳幼児、特に6ヵ月から24ヵ月未満の乳幼児
ハイリスク群に伝染させる可能性が高い群
①.医療・介護従事者、施設従業員
②.ハイリスク群の同居者(小児も含む)
一方、米国では毎年のようにワクチンの効果を調べて公表しています。これ(米国のデータ)によりますと、ワクチン接種によって、65歳未満の健常者についてはインフルエンザの発症を70~90%減らすことができます。また、65歳以上の一般高令者では肺炎やインフルエンザによる入院を30~70%減らすことが出来るとされています。老人施設の入居者については、インフルエンザの発症を30~40%、肺炎やインフルエンザによる入院を50~60%、死亡する危険を80%、それぞれ減少させることが出来るとされています。
このように、高令者や、施設入所者を中心としたハイリスク群において、肺炎などの合併症の発生や入院、死亡といった重篤な被害を明らかに減少させる効果が示されています。これは「重症化を防ぐ」というとてもわかりいやすい例だと思います。
ところで、「超過死亡」という用語をご存知でしょうか?。国民の全死亡数を1年間通して見ますと、ある期間だけ飛び抜けて高いピークが見られる時があります。これが超過死亡です。
これは、通常の病気以外の流行性の病気による死亡が影響したものと考えられます。米国では以前からこの調査が行われており、毎年決まった時期、すなわちインフルエンザの流行期に一致してピークが見られるので、これが主にインフルエンザにかかわる超過死亡であると考えられてきました。
日本でも超過死亡の調査を行ったところ、学童集団接種をしていたころには見られなかった超過死亡のピークが、接種をやめてから再び見られるようになりました。
インフルエンザの流行規模によって違いますが、インフルエンザの超過死亡患者数は平均1万2千人になるという推計もあります。米国では、年間1~4万人の超過死亡が確認され、この死亡の8割から9割は高令者です。このことから、学童集団接種が、高令者のインフルエンザによる死亡をおさえていたと、推測できます。
また、1975年から、2003年までの幼児の超過死亡とインフルエンザワクチンの生産量(下図)を見ますと、学童集団接種は1994年に中止されましたが、接種率は既に1980年代後半から大幅に下がっています。それとは逆に超過死亡が増加しており、幼児(1~4才)の1990年代の超過死亡の合計は約800人になっています。大半の患者の死亡原因はインフルエンザ脳症です。
ワクチンの生産量と超過死亡(脳症)が逆相関していることを考えると、学童集団接種によって、幼児が守られていたようにも思えます。最近では、幼児のワクチン接種も多く行われるようになり、2001年以降は超過死亡は消失しました。
また、2001年から、タミフル、リレンザのような抗インフルエンザ薬が導入されてきましたので、超過死亡の消失は、ワクチンだけではなく抗インフルエンザ薬の効果もあると思います。
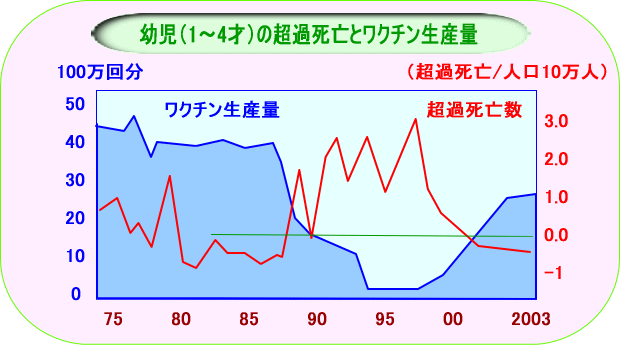
今までお話したことを、まとめますと、
【過去のインフルエンザワクチンに対する間違った評価・誤解】
①.インフルエンザも普通のカゼも区別がつかなかったため、ワクチン接種した人が発熱すると、カゼであろうがなかろうが、インフルエンザと診断された。
②.チョット熱が出たくらいでも、ワクチンは無効と言われていた。
③.上記の①.②.に基づき、「患者数」、「学校・学級閉鎖の数」などの数値による流行規模で、ワクチンの効果を論じていた。
④.医師にも、患者にも、「重症化を防ぐワクチン」という概念がなかった。
⑤.ハイリスク群でのワクチン有効性について考えられたことがなかった。
【現在のインフルエンザワクチンに対する評価】
①.現在では、「インフルエンザワクチンは重症化を防ぐ」ということが、WHOをはじめ世界各国でも広く認められております。
②.この事実に基づいて「ハイリスク群」を主な対象としたワクチン接種が勧告され、その実施が進められるようになり、 その結果、超過死亡数の減少がみられるようになりました。
③.「流行拡大を阻止」については議論が尽きません。インフルエンザの感染を直接防ぐことができない以上、多くの人がワクチンを接種しないと流行拡大を阻止することは難しいように思います。しかし、重症化しなければ他の人への感染も少なくなり、流行規模を小さくすることはできると思います。
私も、毎年インフルエンザワクチンを接種しています。当院の職員も全員接種しています。患者さんに移してはいけないし、自分たちが罹って休んだりしたら多くの患者さんにご迷惑がかかります。
私は、2001年にA型とB型に同時に罹りました。あまり高熱にはなりませんでしたが、インフルエンザ特有の倦怠感は強かったです。タミフルを1日内服しただけで解熱しました。これはタミフルだけの効果ではなく、ワクチンを接種していたから早く治ったと思っています。
当院かかりつけのお子さんで、タミフルを服用すると発疹が見られるため、タミフルを使用できないお子さんがいました。このお子さんは2年続けてインフルエンザに罹りましたが、毎年ワクチン接種しているため、入院することもなく、タミフルも服用せず、点滴もせず、外来通院で治っています。ワクチンの効果といえます。
「インフルエンザワクチンは重症化を防ぐ」ワクチンです。インフルエンザに罹っても、ワクチン接種したお子さんの方が軽症ですし、治りが早いです。
![]() 積極的にインフルエンザワクチンを接種しましょう
積極的にインフルエンザワクチンを接種しましょう![]()
前項でもお話ししたように、インフルエンザワクチンは、接種したからといってインフルエンザの感染を完全に防ぐことはできないのです。重症化を防いでくれるワクチンとご理解下さい。
インフルエンザワクチンが働くしくみを簡単にご説明します。
①.インフルエンザウイルスは、毎年少しずつ構造が変化するため、それに合わせたワクチンが必要になります。前年に流行した株から、翌年に流行しそうな株を予測して作られるわけですが、いつもドンピシャリと一致するわけではありません。しかし、抗体には、よほどウイルスの株が違わないかぎり、似た形のウイルスとは反応し、その働きを中和するという能力がありますので、全くの新型でない限り、十分に効果が期待できます。
②.インフルエンザウイルスは、まず最初に鼻の粘膜で増殖し、それから体内に入り込んで全身を駆けめぐり、時には肺炎、脳炎・脳症、心筋炎などの重篤な合併症を、引き起こします。これに対し、ワクチンは体内に抗体(IgG抗体)を作り、ウイルスが体内に入り込んでからの活動を抑制するように働いてくれます。
ワクチンによってできる抗体は、血中に存在するIgG抗体です。粘膜で働く抗体は、IgA抗体といいますが、現行のワクチンでは、IgA抗体は殆ど作られません。そのため、ウイルスが鼻粘膜で増殖している時は(鼻水、咳、発熱など初期症状の頃)、ワクチンの効果が十分みられない事もあります。つまり、ワクチンは、インフルエンザの感染を直接防ぐことはできないのです。軽度のかぜ症状はやむを得ないと思って下さい。
しかし、この増殖したウイルスが体内に入り込んできた時に、ワクチンによってすでに作られているIgG抗体が、ウイルスの活動を防いでくれるため、重篤な合併症を引き起こさないですむのです。
インフルエンザの重篤な合併症の一つに、脳炎・脳症があります。インフルエンザはとても強烈なウイルスですので、罹れば体内の免疫が必死に頑張ります。正しく頑張れば良いのですが、インフルエンザに対してあまり認識(免疫)がないと、訳がわからず頑張りすぎて、「過剰な免疫反応~免疫の暴走」が起きることがあります。この「過剰な免疫反応~免疫の暴走」が脳炎・脳症を引き起こすと考えられています。ワクチンを接種すると、ある程度の免疫は出来ていますので、インフルエンザに罹ったとき、インフルエンザウイルスを正しく認識し、免疫が暴走することなく、通常の免疫反応にとどまり、脳炎・脳症まで至ることは少ないと思われます。
このように、インフルエンザワクチンは、感染を完全に防ぐのではなく、重症化を防いでくれると思って下さい。
①.ワクチンに使われる成分(卵白など)に対して、アレルギーがある場合
インフルエンザワクチンにはごく微量の卵白成分が残存していますので、強い卵白アレルギーがあると、アナフィラキシーショック(接種後15~30分で、血圧低下、喘鳴、浮腫など)を、おこすことが稀にあります。しかし、卵白成分は極めて微量ですので、卵白アレルギーがあっても、殆どの人は安全に接種できます。
※.当院で、アナフィラキシーが起きたことは今までのところ1度もありません。
②.ワクチンの成分(不活化ウイルス)そのものによる場合
接種部位に発疹、腫脹が出現したり、軽い発熱、頭痛、倦怠感がみられることがありますが、自然に軽快することが殆どです。しかし、稀ではありますが、神経障害を引き起こすことが報告されています。けいれん、麻痺、脳炎、脳症、知覚障害、等が、報告されています。しかしながら、ワクチンとの因果関係が、はっきりしない場合が多く、殆どの場合回復しているようですが、どの程度ワクチンが関与しているかは、明らかではありません。
インフルエンザワクチンによる(と思われる)副作用の頻度は、他のワクチンと比べて決して多くはなく、重篤な副作用は、インフルエンザワクチン100万接種に対して、0.35という数字がでています。これを人数になおすと、2.000万人に7人が副作用がみられるということになります。ただし、これらのうち何例が確実にワクチンが原因なのかということは、判明していません。あくまで、ワクチンがあやしいと思われている場合でこの数値です。
この数値を多いとみるか、少ないとみるかは、さておき、他のワクチンと比較してみると、麻疹(はしか)100万あたり6.00、BCGが1.55、日本脳炎、風疹は0.4~0.6と報告されていますので、インフルエンザが、もっとも重篤な副作用が少ないと言えます。しかし、この数少ない副作用の中には、神経後遺症を残した例も含まれています。(ワクチンとの因果関係は不明のままです。)
最終的には、ワクチンを行うプラス面・マイナス面をよく見極めて、自分にとってプラス面(重症化を防ぐ)が、マイナス面(副作用)を上回ると考えたときに接種をすべきと思います。日本のワクチンは世界で最高水準のワクチンです。副作用は世界中で一番少ないと思われます。が、上述したような副作用もおこりうるということは知っておく必要があります。
最近のインフルエンザの流行の特徴として、短期間に大流行することは殆どなくなりました。しかし、長期間にわたり小流行がダラダラと続く傾向があります。インフルエンザの流行時期を予測するのは難しく、いつインフルエンザワクチンを接種したらよいか、迷われる方も多いと思います。
インフルエンザワクチンを接種してから免疫ができるまで2週間かかります。2回接種の場合、2~4週間おいて接種しますので、1回目接種から4~6週間後に、はじめて免疫ができるということになります。
こうしてできた免疫は5か月は続きます。インフルエンザの本格的な流行期は年によって異なりますが、大体11月下旬~2月中旬です。仮に10月上旬にワクチンを接種したとすれば、11月中旬には免疫ができて11月中旬~4月中旬まで続きますので、本格的な流行期から卒業式・入学式までしっかりとカバーできるでしょう。
つまり、
①.ワクチン接種後4~6週間(2回接種の場合)で効果が現れる。
②.免疫は5か月間持続する。
③.本格的な流行期は11月下旬~2月中旬が多い。
④.長期間にわたり小流行がダラダラと続く。
などということから、10月になったら早めに接種開始するのが望ましいと言えます。
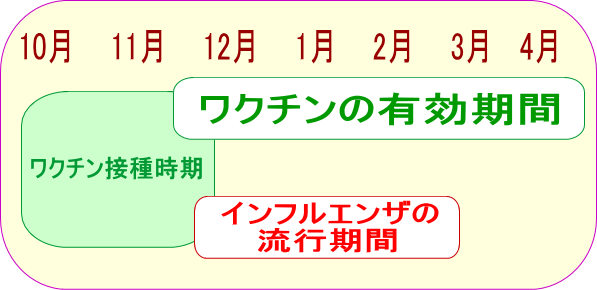
現在のワクチンは、A型2種類(香港型と新型)とB型2種類(山形系統とビクトリア系統の両方)が含まれる4価ワクチンです。
主に流行するB型インフルエンザは、「山形系統」と「ビクトリア系統」と呼ばれる2つのタイプです。この両方が同時に流行することは少なく、以前は一方だけをワクチンに組み入れていましたが、予想が外れると効果が見られませんでした。現在のワクチンは、この両方のB型が組み込まれますので、どちらが流行しても効果を期待できます。
授乳期間中にインフルエンザワクチンを接種しても問題ありません。大丈夫です。インフルエンザワクチンは不活化ワクチン(注2)ですので、ウイルスの病原性がなく、体内でウイルスが増えることもないため、母乳を通して赤ちゃんに影響を与えることはありません。
(注2):不活化ワクチン:細菌やウイルスを死滅させて、免疫を作るのに必要な成分を取り出し、毒性をなくしたワクチン。
妊婦への接種について、本邦のインフルエンザワクチンの添付文書には、「妊婦又は妊娠している可能性のある女性には予防接種上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ接種する
こと。なお、小規模ながら、接種により先天異常の発生率は自然発生率より高くならないとする報告がある」と記載されています。
少しわかりにくい文面ですが、胎児に対する先天異常の発生率は、ワクチンを接種してもしなくても変わらないと理解して良いでしょう。先天異常の問題が理論上は存在しますが、現行のインフルエンザワクチンは不活化ワクチン
(注2)であり、ウイルスの病原性がなく、体内でウイルスが増えることもないため、そのような危険性はほとんどないと考えられてます。また、実際に胎児に悪影響を及ぼしたという報告もありません。
妊娠14週以降の妊婦はインフルエンザの合併症を来しやすく、入院するリスクが高いとの報告があります。このため米国疾病管理予防センター(CDC)は妊娠中にインフルエンザシーズンを迎える妊婦にはインフルエンザワクチンの接種を勧めています。
接種時期は妊娠の全期間において可能とされています。ただし、妊娠初期は自然流産の起こりやすい時期でもあることから避けたほうが良いとする意見もありますので、最終的には現在診ていただいている産婦人科の先生とご相談されるのが良いと思います。
インフルエンザワクチンは一般に生後6か月から行うことができます。1才未満乳児(以下、乳児)では免疫の上昇が低く、十分な効果が見られていません。しかし、ワクチン接種を繰り返すうちに、少しずつ免疫は高まり、インフルエンザに対して抵抗力が出来てきます。
乳児のインフルエンザは軽症が多いですが、幼児期になると脳炎・脳症のような重症インフルエンザに罹ることがあります。インフルエンザはとても強烈なウイルスですので、罹れば体内の免疫が必死に頑張ります。正しく頑張れば良いのですが、インフルエンザに対してあまり認識(免疫)がないと、訳がわからず頑張りすぎて“過剰な免疫反応”が起きることがあります。この“過剰な免疫反応”が脳炎・脳症を引き起こすと考えられています。
乳児の場合、初年度はワクチンの効果が不十分であっても、毎年接種していけば幼児期には少しずつ免疫が高まってきます。その結果、インフルエンザを正しく認識することが出来るようになり、免疫が暴走することなく、通常の免疫反応にとどまり、脳炎・脳症まで至ることは少ないと考えられます。幼児期での脳炎・脳症予防の観点からも、乳児期からワクチンを接種したほうが良いです。
特に、保育園などで集団生活をしている乳児は、接種した方が良いと思います。保育園の保母さんたちも接種すべきです。また、一番身近にいるお父さん、お母さんはワクチンを接種して下さい。お家での感染は殆どご両親からです。
以上より、1才未満乳児のワクチン接種については
①.免疫のでき方が十分とは言えず、初年度はあまり効果が期待できないかもしれません。
②.しかし、毎年接種を続けていけば、次第に免疫はできやすくなると考えられ、幼児期によくみられる脳炎・脳症の予防に効果が期待できると思われます。(積立貯金のように考えればよいと思います。)
③.保育園などで集団生活をしている乳児は、一番感染の機会が多いので、接種した方がよいです。
④.乳児の周囲の人達(保育園の保母さん)や、同居する家族(お父さん、お母さん)が、接種することにより乳児への感染は、かなり防ぐことができます。
予防接種をしないで、冬を迎えることは、丸腰でインフルエンザと闘うことになります。 6か月から24か月未満の乳幼児はインフルエンザにかかると重症化するため、米国ではこの月令の乳幼児にもワクチン接種を積極的に勧めています。ワクチンは重症化を防いでくれます。積極的に接種しましょう。